ニキビができたらまず皮膚科。難治性の場合は自費診療の内服薬も
ニキビは皮膚科で適切な診断を受け治療しましょう。イソトレチノイン(自費診療)という選択肢もあります。
- 英 真希子 副院長

頼れるドクターが教える治療法vol.163
脳神経外科
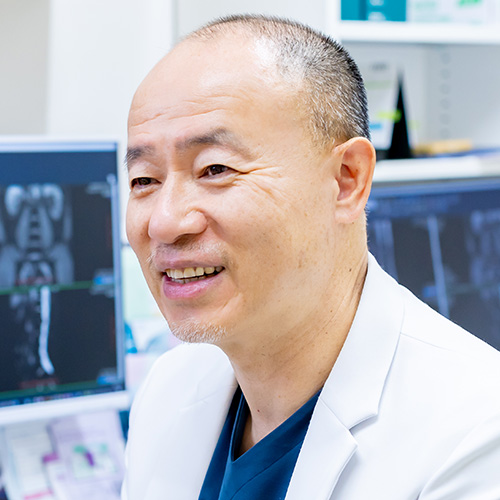
目次
国際頭痛分類では、頭痛を「一次性頭痛」「二次性頭痛」「脳神経の有痛性病変とその他」の3つに分類しています。
一次性頭痛は、脳や脳以外の病気を原因としない頭痛のこと。片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などが代表的な疾患です。二次性頭痛は何らかの病気に起因する頭痛で、脳の病気であればくも膜下出血、脳内出血、硬膜下血腫や脳腫瘍など、重い後遺症や命に関わることから「危険な頭痛」といわれます。ただし、外傷、副鼻腔炎、頚部痛との関連など、脳以外の病気によるものも含まれています。そして「脳神経の有痛性病変とその他」は、帯状疱疹や血管神経圧迫症候群による三叉神経痛、後頭神経痛など、脳神経の損傷や病気が原因で頭痛などの痛みを生じる稀な病気です。

当院では、問診票に記載された内容と診察をもとに症状を推定したあと、MRI検査を実施して画像による判別を行っています。片頭痛が考えられる場合は、HIT-6という問診票にて点数化も行います。頭痛で受診される患者さんは一次性頭痛が多く、危険な頭痛が見つかるケースは少ないです。しかし、まず画像検査によって危険な頭痛を否定することが、受診される患者さんの安心の獲得、正しい診断と適切な治療につながります。危険でなくても、副鼻腔炎や三叉神経痛の区別など、診断の助けになる所見が出ることは珍しくありません。もちろん命に関わるタイプの頭痛が判明した場合には、速やかに専門の医療機関と連携することが可能です。

片頭痛の症状は、ズキズキと脈打つような激しい頭痛で、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。光に不快感や痛みを覚えたり、普段では気にならない音をうるさく感じたりすることもよくある症状です。
また、痛みの発作時以外にも不調が現れます。例えば首や肩の凝り、ダルさ、不安感や集中力の欠如、めまい、食欲不振や異常な食欲増加、感覚敏感などです。こうした症状のせいで、慢性的に気分がすぐれない方も多いですね。

片頭痛の慢性化傾向は、肩凝り、うつ状態、不安感や疲労感など、たくさんの随伴症状を伴いやすく、繰り返すうちに生活の質が低下します。頭痛発作への不安で予定を立てづらくなったり、さまざまなことに消極的になったりすることもあります。単に頭が痛くなるだけではなく、日常生活にマイナスの影響を与える「消耗性の全身疾患」と捉えることが適切でしょう。
片頭痛と上手に付き合っていくには、日ごろの予防治療がとても重要です。日焼けやシミを予防するためにお肌のケアがあるのと同様、片頭痛を減らすための「ブレインケア(脳のケア)」が重要と考えています。

頭痛を起こりにくくする予防薬と、痛み始めで飲む頓服薬から開始します。また、生活習慣の改善も必須です。約1か月継続し、効果があった方はそのまま継続します。一定期間で予防薬も終了できれば理想です。
一方これらの治療で満足が得られない場合は、2021年から保険適用となった、予防注射薬の使用を検討します。
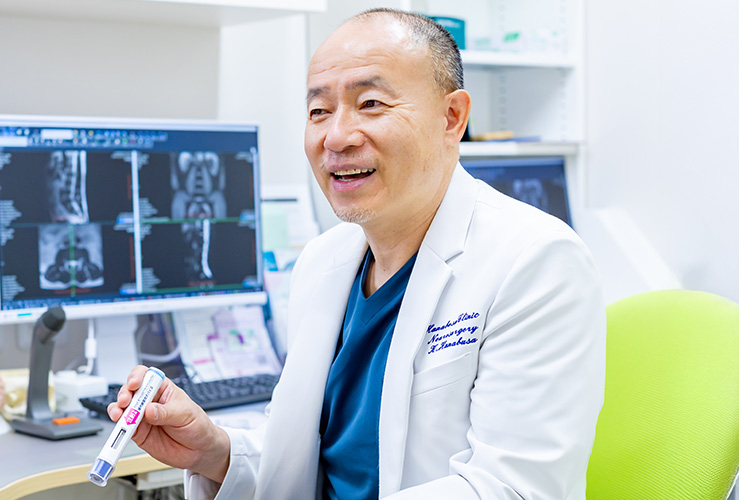
片頭痛の痛みを誘発する原因物質は判明しています。その物質を抑える注射薬(CGRP関連抗体薬)が登場し、片頭痛の治療は大きく進歩しました。基本的に1か月に1回の注射と、症状によってほかの予防薬(飲み薬)や漢方を併用します。在宅自己注射という、自宅で注射できるものです。指導しながら慣れていただきますので、初めは抵抗感があっても多くの方が在宅で実施可能になります。

約9割の患者さんで、「痛みが半分以下」になるといわれています。片頭痛がなくなったという方もいて、患者さんも私自身もその効果を実感しています。眠くなるなどの副作用がなく、多くは数日以内で効果を感じられます。「頭痛はあっても軽くて、頓服薬の必要回数が減った」「頓服薬が効きやすくなる」などの効果が得られる点も、メリットが大きいでしょう。片頭痛の随伴症状の代表である、慢性的な肩凝りや気分の落ち込みなども減っていきやすくなるようです。飲み薬による予防で日常生活が比較的元気に送れるのであれば、そのまま治療を継続して良いと思いますが、そうでない場合は大いに検討していただく価値がありますね。
またこの治療は18歳以上であれば受けることができ、当院には60年間頭痛に悩まれてきた70代の患者さんもいらっしゃいます。長年痛みを我慢し続けている方にはぜひ、片頭痛を楽にできる治療があると知っていただきたいですね。
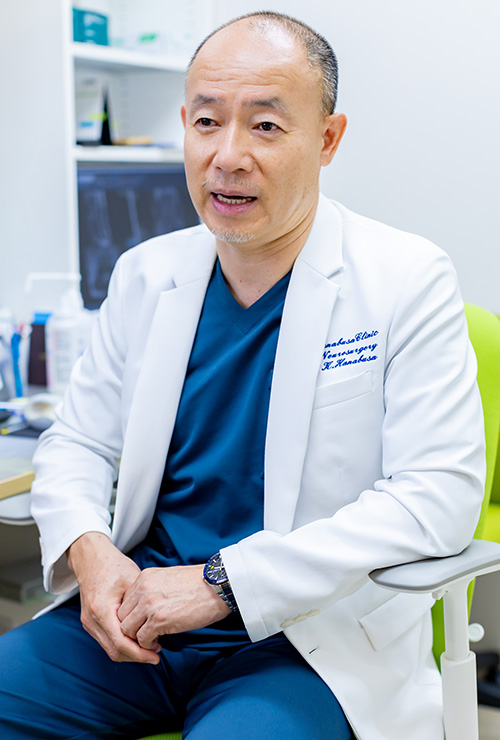

はなぶさ脳神経外科・皮ふ科クリニック 地図を見る

動悸や息切れは心疾患の可能性も。「機器・技師・医師」の総合力で、心臓弁膜症の早期発見を目指します。

患者さんとスタッフが笑顔になれるよう常に考え、一人ひとりに合わせたコミュニケーションを心がけます。

細胞診を含む専門的な甲状腺診療を提供。豊富な知見と技術で、女性のライフステージに寄り添います。