本格的な
リハビリテーション・
運動療法を、四谷三丁目で実践
リハビリテーション・
運動療法を、四谷三丁目で実践
四谷三丁目駅から徒歩2分。広々としたリハビリテーション施設で、身体を本来あるべき状態に近づけます。
- 四谷整形外科リハビリテーションクリニック 東京都新宿区左門町
-
- 幸島 雄太 院長

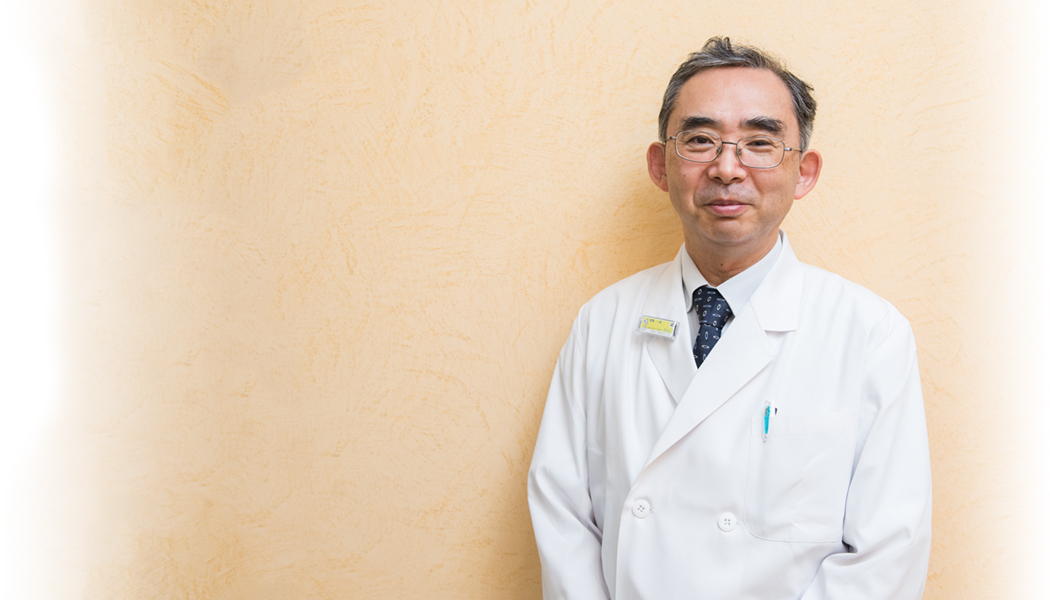
街の頼れるドクターたちvol.050 内科
目次
もともとの専門は腎臓内科で、救急医療に取り組む病院の勤務医として約25年間、急性疾患のほか、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の治療にあたってきました。漢方を本格的にスタートさせたのは十数年前です。実を言いますと、私の家は祖父の代からの漢方医の家系なんですね。時は明治時代に遡りますが、祖父の兄(伯祖父)がマラリアにかかり、一命は取り留めたものの下痢が止まらず、飲食もできずに途方に暮れていたところを、漢方医が見事に治してくれた。これに感銘を受けた伯祖父は自ら漢方医の道に進んだのですが、東洋医学の知見を広めるためには人手が必要だというので祖父を引き込んだのです。こうした事情も手伝って、我が家には東洋医学や漢方の本がたくさんありましたし、勤務医の頃からいろいろな先生のもとに通いながら漢方の勉強を重ねてきました。

患者さまお一人おひとりのニーズに合った“オーダーメイド”の治療です。西洋医学は臓器ごとに診療科が分かれ、病気の原因を細胞レベルで捉えるなど、“ミクロ”な方向で発展を遂げてきました。一方、東洋医学は自覚症状や脈、舌の状態、お腹を触った感触等から全身のバランスの乱れを判断する、“マクロ”な視点で治療を進めます。バランスの乱れ方は、患者さまの病状や生活環境によって異なりますし、風邪の引き始めや治りかけなど病気のステージによっても違います。また、発熱一つとっても患者さまが寒がっているのか、暑がっているのかによって対応を変えますし、脈も、脈拍数のみならず脈の強さや流れ方を重視するなど、西洋医学とは異なる所見を取ります。その意味でも、患者さまお一人おひとりのお話をじっくりと伺い、全身を丁寧に診察することが大切なのですね。

甘くて飲みやすい処方もありますが、あながち間違いではありません。例えば、偏頭痛の患者さまに処方する「呉茱萸湯(ごしゅゆとう)」という、とても苦い漢方薬があります。これを、嘔吐を伴う激しい頭痛発作に悩まされている患者さまに飲んでもらうと「美味しい」という方がいらっしゃるんですね。一説によると、症状にフィットする薬は美味しく感じられるのだそうです。もっとも症状が緩和されていくにつれて、どんどん苦くなっていきますので、まずいという点は変わらないのですが…。

場所柄、東京オペラシティビルや周辺のオフィスビルで働いているビジネスパーソンやお近くにお住まいの方が、生活習慣病の治療や風邪や腹痛等でいらっしゃるケースが多いですね。また、最近は漢方治療を希望して来院される方も少なくありません。漢方治療で特に印象に残っているのは、毎月毎月、扁桃腺を腫らして発熱されていた患者さまです。この患者さまに慢性鼻炎や扁桃炎の治療に用いられることの多い漢方薬「荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)」を処方したら、相性が良かったのでしょう、症状がピタリと治まったんです。「今年の冬は一度も熱を出すことなく乗り切ることができた」と本当に喜んでくださったのが、私にとっても感動的な経験でした。

西洋医学と東洋医学の融合という観点からさまざまな治療を行っていますが、何といっても基本は食生活ですよね。東洋医学には「食毒」という考え方があります。食生活の乱れによって「食毒」が溜まると、体全体のバランスが乱れるという発想です。食生活の改善は心掛けによるところも大きいので、患者さまとしっかりとコミュニケーションを取るとともに、必要に応じて栄養士による指導を行っています。

私たちの役割は「病気を治す」というよりも、患者さまが自らの力で治癒に向かっていくことができるように応援し、支えていくことだと思っています。その意味で、患者さまと「一緒に治す」姿勢を大切にしていきたいですね。目標は「とりあえず行ってみよう」「来てよかったな」と皆さまに言ってもらえるクリニックです。お身体に不安や悩みをお持ちの方はもとより、漢方薬を試してみたいという方にも是非、お気軽に来院いただければと思います。


オペラシティクリニック 地図を見る

四谷三丁目駅から徒歩2分。広々としたリハビリテーション施設で、身体を本来あるべき状態に近づけます。

高度な技術が必要な神経ブロック注射をクリニックで提供。迅速な検査・治療が可能な体制を整備しています。

分院の開業で、さらに豊富な美容医療の選択肢を提供。患者様の理想とする美と健康の実現をお手伝いします。